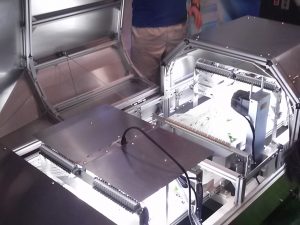農業は常に自然を相手にする仕事です。わかってはいてもあまりの自然の驚異に愕然とさせられることがあります。何の仕事でも自然と向かい合っていますが農業での自然の驚異をお伝えしたいと思います。またこのような出来事を忘れないためにも書き記しておきたいと思います。
平成23年6月の集中豪雨
大雨23年6月 だだちゃ豆畑が水浸しです。これでも少し引いた後です。一日だけでなく数日間雨がやまなかったのが被害に拍車をかけました。

大雨ごの排水路23年6月 1回目の大雨の後の大豆畑と隣を流れる排水路の様子です。排水しきれずオーバーフローして畑に水が入ってきました。

平成22年4月の季節外れの雪
この季節は例年なら乾燥注意穂が出てもいいはずなんですが雪が降りました。全国的に寒い春で5月下旬までこの寒さが続き作物の生育が心配されました。
春の雪 雪が降りトラクターと畑は真っ白になりました。

平成21年12月の大雪
近年は昔に戻ったかのように大雪がよく降ります。
ハウス倒壊 雪の重みでハウスが倒壊しました。

平成19年6月の豪雨による被害状況
梅雨時期に集中豪雨が降りました。ひどいところでは朝方に降った雨が夕方まで引かず、畑ではだだちゃ豆がほぼ全体水に浸かる状態になりました。そのうえ雨上がりに太陽が照りつけたまった水がお湯のようになり根っこが茹でられる状態になりました。結果根っこが腐れ下の葉から徐々に枯れていきました。その後も雨が続き被害は拡大しました。鶴岡市でのだだちゃ豆作付け面積約840haの6分の1が被害にあったそうです。家のだだちゃ豆も被害にあいました。
大雨被害 根がやられ下の葉から徐々に枯れていきました。

冠水 ようやく水が引いていった畑です。
 070626_090845
070626_090845
平成19年4月の降雹被害状況
季節外れの雹が降り定植間近かのだだちゃ豆の苗がめちゃくちゃに傷つけられました。また畑に植えた枝豆の苗もぼろぼろになり本葉が落ちこのまま植えておいても収穫できないものになってしまいます。
雹 右側が降った雹です。左が分かりずらいんですが百円玉です。

雹被害 雹に傷つけられただだちゃ豆の苗です。葉っぱが枝部分から落ち一番大事な本葉が落とされてしまいました。

雹被害 雹被害 畑に植えたレタス(左)とキャベツ(右)の苗です。見るも無残な姿になりました。キャベツのほうがまだましな状態ですが葉っぱがもうチリヂリというかばらばらになりました。ちなみに黒いマルチ(保温用ビニール)も穴が開いているのが見えますがそれも雹によるものです。

平成16年の台風15号、16号による農作物への被害状況です。
自然の脅威を目の前にすると人間の力なんて無力なんだとつくづく実感させられます。被害はだだちゃ豆、水稲、大豆などの販売作物から栗、キウイ、柿などの自家消費の果樹、さらにビニールハウスの破れ、ガラスハウスの破損多岐にわたりました。特に水稲の被害は甚大で庄内地方で何十億の被害だそうです。稲穂の白穂枯れと枝梗枯れ、風邪による擦れ、さらにはうちの近所ではないですが海に近いところでは塩害も起きたそうです。これにより収量はうちのところでコシヒカリで例年の半分くらいと予想されています。ちなみにこの潮風害は文献が残っている限りでは100年以上ぶりのことだそうです。16年は春先の大雨、梅雨末期の集中豪雨、異常な気温の上昇といろいろありましたこんなこともあったんだと忘れないように書き記しておこうと思います。
枝豆畑です。葉っぱが落ちて残っている葉っぱも風邪で擦れてしまったために入れが緑色から茶色になってしまいました。当然実の入りが悪くなったり莢にも傷がつくなどの被害が出ました。

水稲の白穂枯れです。中央の白くなってるのがそうです。台風の強風と、高温での急な乾燥により起きました。これはだいぶ経った後の写真ですが台風の2,3日後は田んぼが真っ白のところ(下の画像)もありました。

白穂枯れの圃場です。田んぼの色が黄金色ではなく白っぽくなっています。。白くなって見えるところが白穂枯れしたところです。そして白穂枯れにより籾の中に実が入りませんでしたので穂が立っています。実るほど頭を垂れる何とやらというのも今年に限っては例外です。

大豆の畑です。枝豆同様葉っぱが落ち擦れて茶色くなりました。草丈も伸びなくなりました。